| No | 自主防災会名 | 訓練内容 | 実施日 | 実施自主防災会による
訓練の所見 | 訓練写真 |
|---|
| 1 | 松高校区自主防災会 | 避難所開設・運営訓練 | 4月15日 | マニュアルに沿った「避難所運営訓練」を実施した。「7時30分に地震発生、直ちに避難」と一斉メールで通達し、避難開始のはずだったが、各担当部署が係仕事をするために、地震発生前に避難所に集結し、訓練のための準備や設営を発生前にしてしまったのが反省点である。全員が、地震発生後に避難してきて準備設営をすることが改善点である。ただし、避難所運営としては、各部屋レイアウトや担当配置はきちんとできていてよかったと思う。間仕切りテントの設営もみんなで確認しながらできてよかった。 | 
|
|---|
| 2 | 高小原町内会自主防災会 | 危険個所の確認、
避難路点検 | 5月14日 | 登下校時における危険個所を保護者と防災士と歩き、「この川が溢れたら通学路から川に落ちるよ」とか、「この高さの屋根には頭に気を付けて」、「ここのブロック塀は倒れてくる可能性がある」とか、「子ども見守り看板や、お助け立ち寄り可能店の存在」等を教えながら歩いた。最後に振り返りをして、防犯笛やアルファ米、ビスケットをお土産に渡した。実際に雨の時にも実施してもいいかもしれないと思った。参加者も20家族参加いただき、実りある活動になった。継続して新1年生には伝えていきたいと思います。
| 
|
|---|
| 3 | 植柳校区自主防災会 | マイタイムラインを
活用した訓練(避難訓練) | 5月30日 | 校区住民に訓練の参加をしていただくためには、まず役員達がマイタイムライン、それを用いた訓練を知る必要があると考えたので、校区自主防災会における役員である各町内長、さらに消防団、ふれあい委員、婦人部の代表者で連携してマイタイムラインを用いた避難訓練を行った。訓練を実際に行うことで、役員におけるマイタイムラインの知識醸成が図れ、校区におけるマイタイムラインを広める第一歩になったと思う。 | 
|
|---|
| 4 | 下有佐自主防災会 | 救急救命訓練
(心肺蘇生法) | 10月29日 | 熊本地震から7年ということもあり、住民の防災意識も薄れてきたと思うので、高めるために本訓練を計画した。体育祭という住民が集まる機会を利用することが非常によく作用し、訓練単体で行うより多くの住民の防災意識を高めることができた。 | 
|
|---|
| 5 | 高小原町内会自主防災会 | 初期消火訓練 | 12月3日 | 今回の初期消火訓練には、幼児からご年配の方まで幅広い年齢層の方々に参加していただきました。今後は、さらに家庭で火を扱う機会が多い方々の参加を呼び掛けていきたいと思います。 | 
|
|---|
| 6 | 陣内地区自主防災会 | 初期消火訓練 | 1月7日 | 思っていた以上の住民の参加者があり(特に能登半島地震もあり)、防災に対する意識を高めることができた訓練になったと思います。これを継続してやっていきたいと思います。 | 
|
|---|
| 7 | 麦島校区自主防災会
(千反町一丁目) | 炊き出し訓練、
初期消火訓練 | 1月9日 | 炊き出し訓練及び消火訓練も事前に役割分担等確認のうえ訓練を行ったので、会長の指示のもとスムーズに行うことができた。 | 
|
|---|
| 8 | 麦島校区自主防災会
(古城町第二町内) | 危険個所の確認、
避難路点検、
炊き出し訓練 | 2月4日 | 能登震災を見るにつけ、手押しポンプの必要性を痛感する。今回歩いたコースでは、墓地の給水用に手押しポンプが1台あるのを発見、但しこわれていて水は上がってこない。しかし一寸した修繕で使用可能になると思われる。これ等の修繕をどのようにしたら可能になるか考えていきたい。 | 
|
|---|
| 9 | 千丁町北吉王丸
自主防災会 | 避難訓練、
初期消火訓練 | 2月4日 | 能登地震発生による危機意識の高まりが感じられた。
訓練を通して地域の一体感が図られた。
地域消防団が積極的に参加してくれた。 | 
|
|---|
| 10 | 松崎町第二町内
自主防災会 | 避難訓練、
初期消火訓練、
炊き出し訓練 | 2月18日 | 参加いただいた住民へ、訓練のアンケートを実施しており、そのアンケートにもあるように、防災訓練等の必要性を参加者の子どもから高齢者まで共有できた。 | 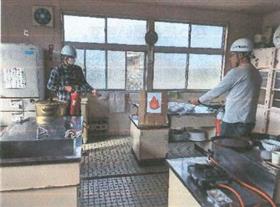
|
|---|